阪神・淡路大震災から31年を迎える中、堺市に移転した近畿大学病院が、将来発生が懸念される南海トラフ地震への備えを強めている。耐震性を大幅に高めた新病院は災害拠点病院に指定されており、大規模災害時には多数の重症患者を受け入れる「主戦場」になることを想定している。
近畿大病院救命救急センターでは、災害派遣医療チーム(DMAT)の隊員が30人以上登録されている。DMAT責任者の太田育夫医師は、能登半島地震での派遣経験を踏まえ、「現在は行政や警察などとの情報共有体制が整い、医療資源の偏りを防げるようになってきた」と話す。
南海トラフ地震では、和歌山県沿岸部の医療機関が津波の影響を受ける可能性が高く、十分な医療活動が難しくなると指摘されている。海から離れた立地にある近畿大病院について、太田医師は「大量の患者を受け入れる役割を担うことになる」とし、DMAT派遣と並行して病院内での医療提供が中心になるとの認識を示す。
救命救急センター長の篠崎広一郎医師も、「全ての命を救えるわけではない現実を受け止めつつ、救える命を確実に救う体制を整えることが重要」と語る。災害時には全国から医師が集まることを想定し、病院の司令塔として医療資源を最大限に生かす役割を果たしたいとしている。
阪神大震災を教訓に1996年に始まった災害拠点病院制度は、現在全国で約780病院が指定されている。近畿大病院では、医師だけでなく保健所や行政、警察との「顔が見える関係」を平時から築くことが、今後の大規模災害対応の鍵になると強調している。







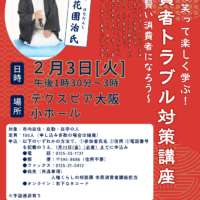
この記事へのコメントはありません。