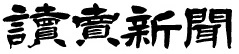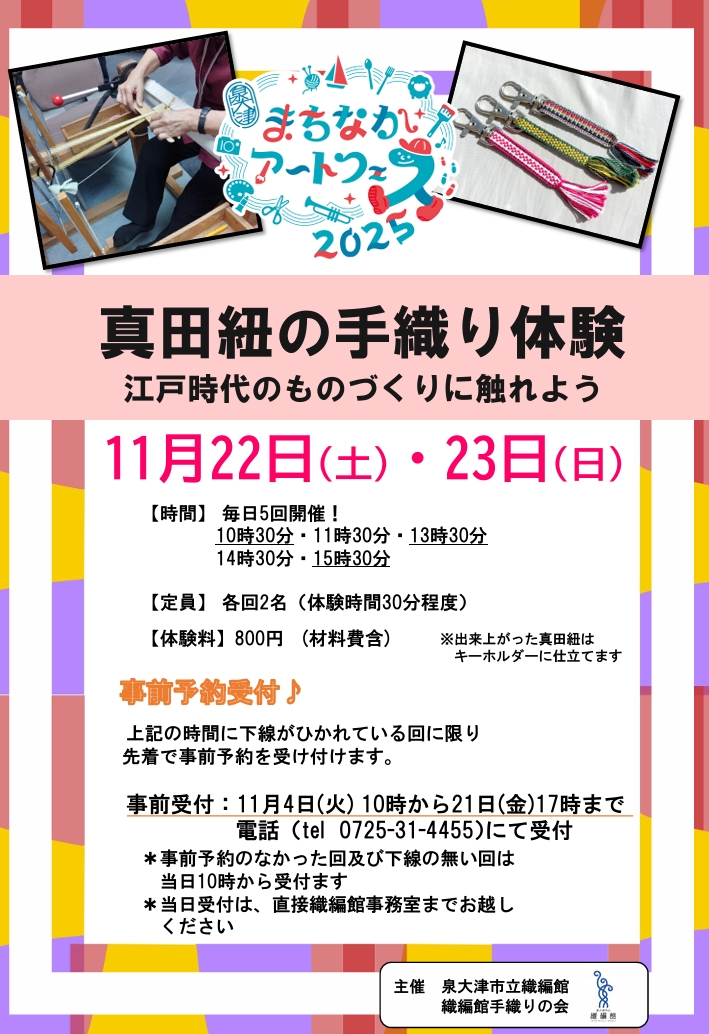「だんじりを支える車輪はどのようにして作られるのですか」。大阪府岸和田市に住む小学1年の知り合いの男の子から質問を受けました。
大阪府南部では、秋に各地で、だんじりが疾走します。中でも、「岸和田だんじり祭」は、スピードを落とさずに方向転換する豪快な「やりまわし」で知られます。
岸和田で生まれ育った私は、だんじりと聞くと血が騒ぎます。9月と10月には3歳の娘を連れて見に行きました。でも、車輪については「木製だった」という程度しか知りません。そこで、市内でだんじりを作っている大下工務店の代表、大下顕広さん(40)に話を聞きに行きました。
大下さんによると、車輪は、正式には「 駒 」と呼びます。伝統的にマツ材が使われてきました。クロマツの丸太(直径60センチ以上)を輪切りにして形を整えます。樹齢100~150年以上になる原木です。乾燥すると駒が割れるため、水に浸して保管し、祭りの直前に乾かして使用します。岸和田城の堀の水に浸していたこともあるそうです。
実は、「こうした伝統的な駒は現在、少なくなっている」と大下さん。代わりに主流になっているのは、製材した細かなパーツを組み合わせた「 組駒 」です。
背景にあるのは、マツ材の減少です。農林水産省の統計では、アカマツ・クロマツの国産材供給量は45万3000立方メートル(2024年)で、50年前と比べて9割弱減少しました。マツ枯れが深刻化したことなどが理由です。
大下さんは「木は100年以上かけて育つのに、駒は1年で使えなくなることもある。地域の祭りで使い続けるには価格が見合わなくなった」と話します。
そこで、大下さんの父・孝治さん(73)が十数年前、「大工やからこそできる駒を」と生み出したのが「組駒」でした。波のように木材に切り込みを入れ、約60個のパーツを組み上げていきます。
素材は、国産と比べて弾力のあるニュージーランド産などのマツを使います。大下さんは「丸太のように芯から割れる心配もなく、水に浸す手間もありません。間伐材を使用するので、環境にも優しい」と教えてくれました。
「組駒」は2013年度、岸和田市などが優れた特産品をたたえる「岸和田ブランド」に登録されました。
「組駒」には難点もあります。伝統的な駒に比べ、駒が硬くなり、走らせるとガタガタと揺れてだんじりに負担がかかり、衝撃で彫刻が折れたこともありました。
大下さんは、内部にゴムを入れた改良版の「組駒」を開発。衝撃を吸収するほか、外側の木を張り替えることで長く使えます。この秋、この「組駒」を採用した町の人たちから「乗り心地も良くて、 後梃子 がとりやすい(方向転換が楽になった)」と感謝してもらえたそうです。
現在、岸和田市では「組駒」が6~7割近くといい、東海や九州の祭りでも使われているそうです。大下さんは「祭りを第一に考え、時代に合わせて技術を進化させていきたい」と話していました。
みなさんの地域では、伝統の祭りを残すため、どんな工夫をしていますか。聞かせてください。
【今回の担当は】辻井花歩(つじい・かほ) 岸和田市出身。大阪市内の高校に通っていた時のあだ名は「岸和田」で、誇らしかった。