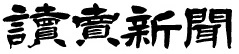岸谷勢蔵画 建物疎開 変わりゆく姿描く
堺市では戦時中、空襲時の延焼を防ぐために家屋を取り壊す「建物疎開」が行われた。戦争で街並みが失われる前に郷土画家の岸谷勢蔵さん(1899~1980年)は絵筆を走らせ、空襲で焦土となった姿も描き残した。戦争で変わりゆく街を描いた作品は、今も戦争や平和の意味を問いかけている。(前川和弘)
岸谷さんは市中心部の宿院周辺で生まれ育ち、戦前戦後を通じ、ふるさと堺の風景や人々の暮らしを描き続けてきた。
建物疎開は空襲による延焼防止を目的に全国の都市部で行われた。堺市でも1944~45年にかけて約3600戸が取り壊され、約1万2000人が立ち退きを余儀なくされたとされる。市は当時、 変貌 する街の景観を後世に伝えようと、岸谷さんら地元の作家に絵や写真、文字で記録にとどめるよう依頼した。
岸谷さんは、鉄道の駅や書店、喫茶店などが並ぶ宿院本通り(現在のフェニックス通り)の約2キロをつぶさに描き出し、横幅20メートル以上の作品に仕上げた。絵は「堺市第一次疎開地区記録」としてまとめられ、市立図書館のデジタルアーカイブで閲覧できる。
文化観光施設「さかい利晶の杜」(堺区)には、この記録などを基に、路面電車が走り、町屋が軒を連ねる堺の街を再現したジオラマも展示されている。市博物館の学芸員、矢内一磨さん(61)は「建物疎開で壊される街並みを絵で記録する取り組みは他では類を見ない」と評する。
堺市は45年3月から計5回、米軍機の空襲を受けた。岸谷さんは約1800人が犠牲となった7月10日の「堺大空襲」の翌日、焼け野原となった街に向かい、その姿も絵にしている。孫の瀬谷ゆりかさん(65)は「祖父は自分が育った街への思いが強かったのだと思う。絵が街の貴重な資料となっていることを誇りに思う」と語る。
空襲を受けた街を描いた絵は、市立平和と人権資料館(中区)の企画展で9月28日までパネル展示されている。資料館の担当者は「岸谷さんの絵などから戦争で焼け野原になった堺が、復興して今があるということを感じてほしい」と話している。