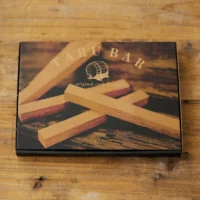大阪府堺市。堺旧港の南に広がる市営大浜公園内に大浜公園相撲場がある。敷地は約4,200m²、収容人数は約2,400人。一辺6.7mの正方形の土台に土を盛り、直径4.55mの円形部分が勝負俵で囲まれた本土俵を含め、3つの土俵が設置された全国でも有数の規模を誇る相撲場だ。大相撲の現横綱・大の里らも活躍した全国学生相撲選手権大会をはじめとする多くの大会が開催され、「アマチュア相撲の聖地」とされている。
でも、堺に相撲の聖地があるなんて、一体どういうことやろう?
「堺に相撲場があるんです」と聞いて、「はっ?」と訊き直した。3月、大阪で大相撲の春場所が行われるのは、エディオンアリーナ大阪と名前が変わった旧大阪府立体育館だ。
よく聞くと、プロの力士による大相撲ではなくて、堺市の大浜公園相撲場では、大学対抗の個人戦・団体戦の全国学生相撲選手権大会を、東京の両国国技館と隔年で開催。実業団や女子相撲なども行われているそうだ。
大学対抗戦の会場というなら、大浜公園相撲場は野球における神宮球場、ラグビーにおける国立競技場(今年2025年は秩父宮ラグビー場で開催)みたいなもんでしょう?
野球やラグビーに比べて、相撲は競技人口が少ないとはいえ、あまりにも知られてなさすぎるやん。
一大レジャーランドだった大浜公園
相撲場がある大浜公園は1879(明治12)年に誕生、堺の市立公園としては最も古い歴史を誇る。その前身は幕末、黒船の来航に備えて砲台を築造した砲台場、いわゆる「お台場」だ。東京にもお台場があるが、江戸幕府は堺にも造っていたのだ。
明治維新後、この砲台跡地を整備し造成されたのが大浜公園で、海水浴場や海水を温めて薬湯とした潮湯の施設、料理旅館、公会堂などが造られた。
1888(明治21)年、大阪と堺を結ぶ日本初の私鉄・阪堺鉄道(現・南海電車)が開通。海水浴や潮湯に興じ、近海で獲れる魚料理を味わうことができる海辺の観光地として賑わうようになる。
1903(明治36)年、「第五回内国勧業博覧会」が、第一会場の大阪の天王寺と、第二会場の堺の大浜公園で開催された。大浜公園に誕生した水族館では、天井をガラス張りにして魚を見上げることができる大水槽が設けられ、国内初の本格的水族館として人気を博す。
その後、堺市立水族館として堺市が運営し、1934(昭和9)年の室戸台風により大破、再建。東洋一の規模を誇るも戦後、臨海工業地帯が造られたことで大浜海岸がなくなり、1961(昭和36)年に閉鎖した。
大正時代には、大浜潮湯というレジャー施設も建てられた。ヨーロッパのコテージ風の建物で、食堂や劇場、遊戯場などが楽しめる、今でいうヘルスセンターのようなものだ。湯に浸かる人、夕涼みに来る人、海水浴に来る人などを目当てに、少女歌劇も行われた。大浜海岸は、関西有数の海浜レジャーランドだったのだ。
学生相撲大会の生みの親・佐多愛彦
1909(明治42)年、大阪大学の前身・大阪府立高等医学校の校長・佐多愛彦(さた・あいひこ)の提唱により、大阪毎日新聞が主催となり、同市の浜寺公園で学生相撲大会を開催。好評だったことから舞台を大浜公園に移し、1919(大正8)年、第1回全国学生相撲大会が開催された。
1871(明治4)年生まれ、鹿児島県出身の佐多は、東京大学医学部撰科を卒業後、大阪医学校の教授となり、1897(明治30)年にドイツへ留学。最先端の細菌学の知識を得て帰国した。折しもペストが大流行していた大阪で、ペスト対策に奔走。その功績が認められ、1902(明治35)年、32歳で府立大阪医学校の校長・同病院長に就任する。
1905(明治38)年、内科の一角に全国初の「肺癆(=肺結核)科」を新設。また、後の阪大微生物病研究所の核となる「竹尾結核研究所」の所長に就任し、結核撲滅の先進的な役割を果たした。
さらには大阪医学校、府立大阪医学校、大阪府立高等医学校など改称を重ねた同学校を、現在の大阪大学創設の礎となる大阪府立医科大学へ昇格させた。大阪大学創設の恩人である佐多の胸像は現在、吹田の大阪大学医学部正面に設置されている。
その佐多愛彦は、無類の相撲好きだった。自身が校長を務める学校で剣術や柔道、相撲を選択必修科目とし、相撲部屋に指導を仰いだ。こうした動きに周辺の学校が続き、学生相撲が普及し始めると、前述の学生相撲大会を企画した。
以降、大学対抗戦による全日本学生相撲選手権大会は戦時中を除き、現在まで開催されている。個人戦優勝者の学生横綱には、以前このコラムでも紹介した堺市内の刀匠、水野鍛錬所の水野淳氏が作る「堺大浜記念刀」他が贈られる。団体戦優勝校には、優勝旗や高松宮記念杯、内閣総理大臣杯などと共に「佐多愛彦賞」が授与されている。
大阪毎日新聞が学生相撲大会を主催した理由は定かではないが、1901(明治34)年、大阪毎日新聞は新聞社として主催する初のスポーツ大会「50マイル長距離健脚競争」を堺の大浜で実施、10万人の観客を集めた。他にも、長距離水泳大会(大阪・築港~兵庫・御影魚崎間)や全国中学校庭球大会を主催するなど、スポーツ振興に力を入れた。
また、最初に相撲大会が開催された浜寺公園には当時、結核の研究所と診療所を兼ねた施設(浜寺石上療養所)があり、大阪毎日新聞の社主・本山彦一(もとやま・ひこいち)も浜寺に住んでいた。ここからは勝手な想像となるが、結核を専門とする佐多が、浜寺を訪れて本山と親交を深め、学生相撲大会を浜寺公園で、という話になったとしてもおかしくはない。この時代にタイムトリップして、是非話を聞いてみたい。
日本書紀にも書かれた堺と相撲
そもそも堺と相撲の関わりは古い。『日本書紀』に登場する出雲国出身の野見宿禰(のみのすくね)が、大和国の当麻蹶速(たいまのけはや)と相撲を取り、勝った功賞として堺市堺区石津町(いしづちょう)の石津神社の神主になったとの言い伝えがある。
堺市文化財課非常勤職員の井溪明(いたに・あきら)氏によると、江戸時代前期には堺で相撲興行が行われていたという。
「江戸前期、今からおよそ400年前に描かれた『住吉祭礼図屏風』は、住吉祭の神輿渡御、住吉大社の神輿を堺の宿院頓宮(しゅくいんとんぐう)にお迎えする、通称「おわたり」と呼ばれる神事を描いたものですが、その絵の右上に野相撲を行っている様子が描かれています。江戸中期には、堺の戎島(えびすじま)で相撲興行が何度も開催されたことが記録に残っていて、少なくともその頃には、江戸・大坂・京都と並び、堺も有力な興行場所となっていたと思われます。勧進元となる親方衆の金持ちがいたんでしょうね」
大浜相撲場を堺の起爆剤に
去る7月7日、新聞社や他メディア、旅行社など約110人を招き、「SUMO SPIRIT in SAKAI~Discover the Power of Tradition~」というプレス発表イベントが大浜公園相撲場で開催された。相撲甚句に始まり、元力士による本格的な相撲の実演や競技方法、土俵作法を披露した他、元力士と取組みを行ったり、塩を撒いたりとリアルな相撲文化に触れることで、相撲に、そして大浜公園相撲場に関心を持ってもらおうと企画されたものだ。
イベントを企画した相撲プロジェクト実行委員会の藤井万寿美(ますみ)さんは、こう話す。
「こんなに立派な相撲場があるのに、学生相撲やアマチュア相撲など限られた時にしか中に入ることができません。堺市の文化遺産として有効活用していくことで、その存在を地元の人をはじめ多くの人に知ってもらい、堺を訪れてもらうきっかけになれば。また、こうしたイベントを定期的に開催することで、元力士の皆さんが活躍できる場作りに繋げていきたい」
確かに、これほどの施設があるのに使わないのはもったいない。次回、大浜公園相撲場での相撲体験イベントは10月頃、一般の人も参加して行われる予定だ。
海外では以前から日本の相撲人気は根強く、インバウンドの観光客も見込めるだろう。大浜相撲場が、以前のような活気を取り戻すのはそう遠い未来ではない、と思う。
大浜公園相撲場
〒590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町4丁
電話:072-225-4421