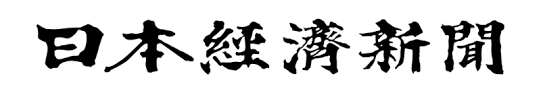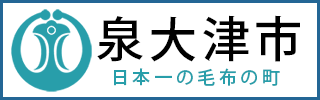堺市は1日、中心市街地で計画中の自動運転バスについて、2025年度中に国の補助金を得て実証実験すると発表した。一部の運転操作をシステムが支援するレベル2で、路上カメラを組み合わせたり路上駐車を回避したりする。前年度は補助金が採択されず見送っており、3年ぶりの実験となる。30年度の本格運行に向けて前進する。
自動運転バスの「SMI都心ライン」は、南海電気鉄道の堺駅と堺東駅の間の約1.7キロメートルを結ぶ構想。今回の実験は10月から26年2月までで、22年度に続き2回目となる。南海バス、パナソニックシステムネットワークス開発研究所、関西電力送配電などが協力する。費用は2億円弱とみられ、国からの補助金約7200万円を充当する。

前回の実験もレベル2だったが、今回は複雑な状況への対処をめざす。車線や歩道を横切って曲がる場所では、車両に搭載したカメラだけでは対向車で死角が生じる恐れがあるため、路上のカメラと組み合わせる。路上駐車のスペースを十分に確保することで、バスがセンターラインを越えずによけられるようにする。
このほか歩行者の飛び出し、車の割り込みといった状況を3D(3次元)の仮想空間で再現し、どうすれば安全を確保できるかをシミュレーションする。26年度も追加の実験を予定しており、27年度には特定条件下で運転手が介在しないレベル4を一部区間で実現することをめざす。
堺市にとって、東西の中心市街地を結ぶ公共交通は長年の課題となっている。一時浮上した次世代型路面電車(LRT)の計画は、コストがかかりすぎるとして竹山修身前市長が凍結。19年に当選した現市長の永藤英機氏が自動運転バスの構想を打ち出した。
これに対し議会は、費用対効果が小さいと指摘。24年度の当初予算では実験費用を削った修正案を可決し、永藤氏が議決のやり直しを求める「再議」に付した。結局、国からの補助金がおりずに実験が見送りとなった経緯がある。