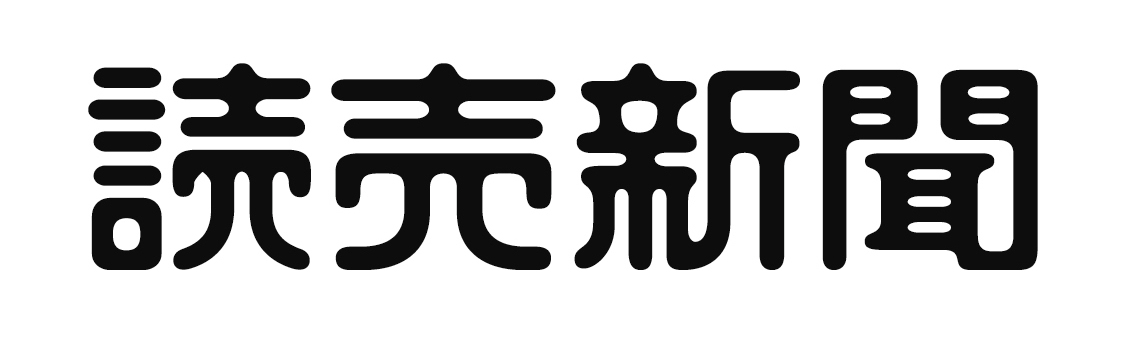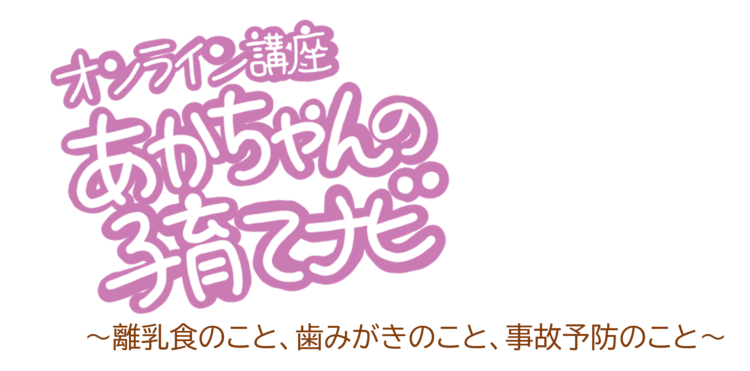大阪湾に生息するスナメリの研究に取り組んでいる神戸大の岩田高志助教(動物生態学)らのチームが、2022~24年度に実施した調査の結果をまとめた。関西空港周辺で多く確認され、湾内に定着しているとみられることや、食性などがわかった。今後、調査結果を論文として発表するとともに、関係機関にも呼びかけて生態系の保全を訴える。(行成靖司)
スナメリはイルカと同じハクジラの仲間で、体長1・5~1・7メートル、体重50~60キロ・グラム。国際自然保護連合(IUCN)の絶滅危惧種に指定されている。熱帯から温帯アジアの沿岸に広く分布し、水深10~20メートルの浅い水域を好む。
日本では大阪湾のある瀬戸内海、九州地方の大村湾や有明海・橘湾、東海地方の伊勢湾・三河湾など5海域に分布している。イルカのようなくちばしと背びれがなく、水面でジャンプすることもないので観察が難しく、詳細な生息数や生態はわかっていなかった。
大阪湾では関空周辺での目撃情報も多く、岩田助教は神戸須磨シーワールド(神戸市須磨区)や海遊館(大阪市)などと共同で、22年度から3年間調査した。船上からの目視観察や、水中に含まれるスナメリのDNA断片を調べる環境DNA調査、水中にマイクを設置して鳴き声の測定を行ったほか、座礁などで死んだ個体から何を食べているかも調べた。
この結果、1年を通して1~5地点で多い時で20個体を確認。湾内全域でDNAが検出されたことから、定着していると推測された。中でも関空周辺が多かった。周辺は禁漁区で、空港島の護岸が藻場や魚礁となって餌の魚が豊富にいるほか、大型船が航行しないため、生息しやすい環境にあるとみられるという。
大阪湾の16個体と播磨灘の9個体から、餌となった2802匹の生物を確認した。最も多いのはヤリイカで18個体が食べていた。次いでテンジクダイ(11個体)、コウイカ(9個体)、ハゼ(7個体)の順だった。播磨灘で見つかった9個体は、タコ・イカ食の傾向があり、不漁が続くイカナゴは検出されなかった。
岩田助教は、「人間活動によって豊かになる『里海』という生態系もある。関空の魚礁や藻場再生などに取り組む大阪湾はまさに里海。海洋生物と人が共存できるモデルケースとなる」と指摘。海と人との持続的な共生を目指し、研究機関や自治体、漁協などで構成する「大阪湾里海プラットフォーム」の設置を提言しており、「どのように維持していくのかが課題で、継続的な調査が必要だ。行政や市民、企業などにも協力を呼びかけたい」と話している。