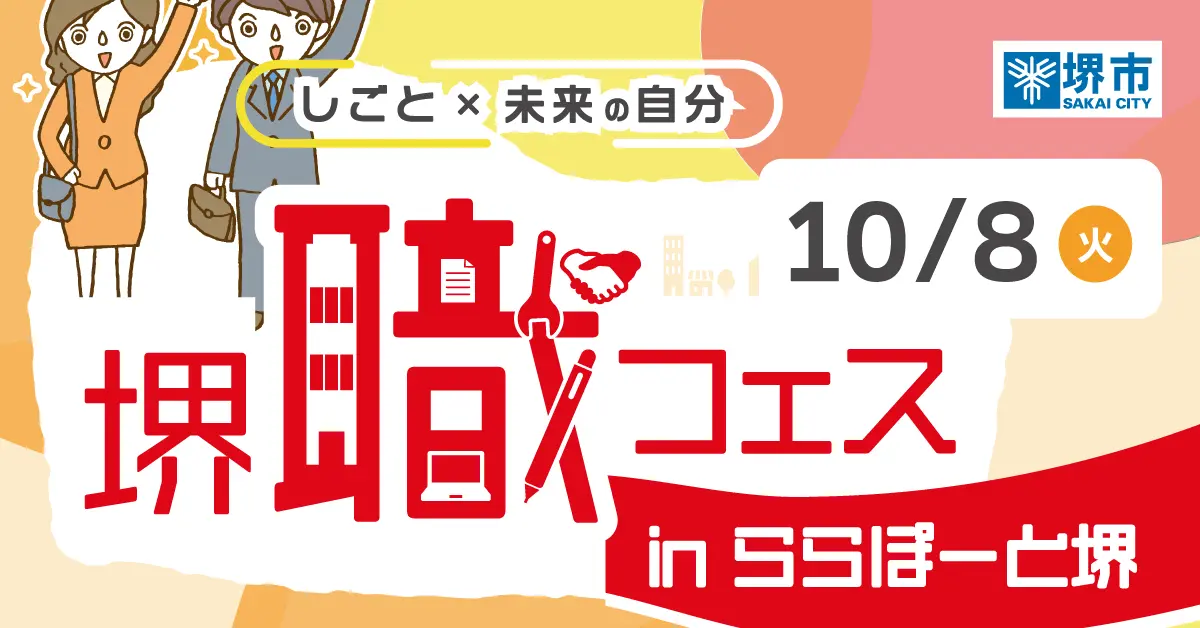使用済みの食用油などを原料とする航空機の次世代燃料=SAFの製造が先月(4月)から大阪・堺市で本格的に始まる中、1日、この国産のSAFが初めて関西空港の航空機に供給されました。
関西空港では1日、国産のSAFが初めて航空機に供給されるのを記念する式典が開かれました。
はじめに、製造会社の担当者で日揮ホールディングスの秋鹿正敬 専務が「ここに国産SAFの実用化を宣言します」とあいさつしました。
このあと、関係者は駐機場に集まり、SAFが使われている上海行きの航空機の出発を見送りました。
SAFは従来の燃料に比べて二酸化炭素の排出量が少ない次世代の航空燃料で、これまで航空会社では海外から購入するなどしていました。
今回のSAFは堺市に新設された製油所で製造されたものです。
この施設では年間3万キロリットルが生産される計画で、今後、国内各地の空港に供給されることになっています。
SAFをめぐっては政府が脱炭素社会の実現に向け、2030年時点で国内の航空会社が使う燃料の10%をSAFにする目標を掲げていて、関西では和歌山県で2028年度の稼働を目指し、年間40万キロリットルを生産する設備の建設が予定されるなど、動きが活発になっています。
【SAFはどう航空機に給油される?】
航空機の次世代燃料=SAFは直接、航空機に給油されるわけではありません。
そもそも航空燃料は、タンカーによって空港に運ばれたあと、巨大な円柱状のタンクに蓄えられます。
空港の地下には網目のようにパイプラインが張りめぐらされていて、燃料はこのパイプラインを通じて駐機場の真下まで送られ、給油会社の専用車が航空機に給油します。
今回、どのくらいの量のSAFが関西空港に供給されたかは明らかにされていませんが、いつもと同じようにタンクに入れられたということです。
その結果、SAFはタンクの中で従来の航空燃料と混ざり、実際には薄まった形で、関西空港のさまざまな航空機に少しずつ提供されたことになります。
ただ、これではどの航空会社がどの程度、二酸化炭素の削減に貢献したのか、はっきりしません。
このため、SAFの製造会社は国際的なルールに基づき、購入した量にあわせて、二酸化炭素の削減量などを記した「証書」を航空会社に発行しています。
そして、それぞれの航空会社はこの「証書」を根拠に削減実績などを公表することになっています。