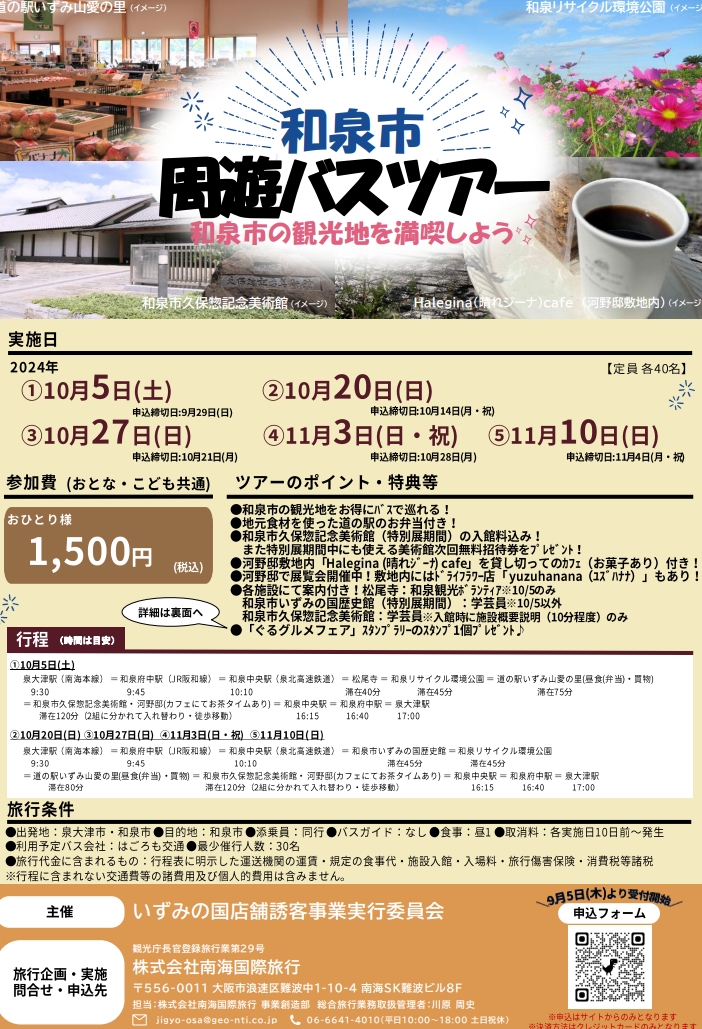高度経済成長期、東京・大阪といった大都市近郊には多くのニュータウンが誕生した。その背景には、日本の産業が農業から工業へと大転換していたことが挙げられる。
それら工業化に伴って経済発展する大都市には農村から多くの労働者が流入。そして、その近郊には労働者の住処となるニュータウンが整備された。
大阪圏では、大阪市から近い千里丘陵に計画人口を約15万人とした「千里ニュータウン」が築かれることになったが、泉州エリアにも約18万人の「泉北ニュータウン」が計画された。
人口規模だけを見れば、千里ニュータウンよりも泉北ニュータウンに大きな期待が寄せられていた。しかし、泉北ニュータウンの人口はピーク時でも約16万人程度で、その後は若い世代の転入が進まずに衰退局面へと突入。昨今は高齢化という問題が深刻化している。
人口減少と高齢化は泉北ニュータウンだけに起きている現象ではなく、日本各地で見られる。しかし、ニュータウンの高齢化は顕著のため、その問題がことさらクローズアップされる。
高度経済成長期に大きな期待を背負いながらも、泉北ニュータウンはどうして成功せずに衰退してしまったのか?
「住宅難」解消のためのニュータウン計画
今年4月1日、大阪府堺市と和泉市を走る泉北高速鉄道(泉北高速)が南海電鉄に組み込まれて南海泉北線として再出発した。
泉北高速は堺市の中百舌鳥駅と和泉市の和泉中央駅を結ぶ約14.3キロメートルを結ぶ路線で、その沿線には高度経済成長期に泉北ニュータウンが計画・造成された。
言うまでもなく、泉北高速はニュータウン住民の足となることを想定して整備されている。泉北高速を使えば、泉北ニュータウンから大阪市中心部までは1時間程度で移動できる。
泉北ニュータウンが計画されたのは、当時の大阪市が抱えていた住宅難という行政課題を解消するという意図があった。
大阪府は住宅戸数を供給するべく、率先してニュータウンの開発を主導した。これに堺市も協力して、泉北ニュータウンには大阪府や日本住宅公団などの集合住宅が多く建設されていく。
こうして、泉北ニュータウンは1967年にまちびらきを迎える。しかし、この時点で泉北高速は開業していない。
泉北高速は大阪府が出資する大阪府都市開発という第3セクターが運行する鉄道だったが、大阪府都市開発は鉄道事業だけを所管する事業者ではなかった。そこには、経営的な判断も少なからずあった。
「面的開発」と「線的開発」
泉北ニュータウンは前述の通り、大阪市の住宅難を解消するために計画された大規模な住宅地である。それを整備するためには、広大な土地が必要になる。
同時期に整備された千里ニュータウンと同じく、それまでの「泉北ニュータウン」計画地は無人の荒野と形容できるほど何もない土地だった。
そうした大地を切り開いて住宅地を造成するのだから、そこに鉄道を建設しても利用者はいない。採算度外視で赤字路線を運行してくれるような鉄道事業者がいるはずはなく、そこで大阪府が出資する鉄道が泉北ニュータウンの足となることが発案された。
しかし、いくら大阪府が出資する第3セクターとはいえ、赤字必死の路線だけを担わせることはできない。そうした経緯から、大阪府都市開発は東大阪・北大阪流通センターのトラックターミナルとりんくう国際物流センター運営・開発も手がけることになった。
こうして都市開発事業で収益をあげ、その黒字で鉄道の赤字を穴埋めするというスキームが生み出された。
そんな難産の末に、泉北高速は1971年に中百舌鳥駅―泉ケ丘駅間をまず開業する。そして1973年には泉ケ丘駅―栂・美木多(とが・みきた)駅間を、1977年には栂・美木多駅―光明池駅間を開業させた。
泉北高速はひとまとまりに開業するのではなく、わずか6年という短い歳月ながらも段階的に延伸していった。
泉北ニュータウンも、この鉄道の開業に合わせて駅ごとに周囲の住宅や施設を整備する形で進められていった。そのため、駅を中心に街が広がる「面的開発」となったのだ。それゆえ、駅と駅の間にはめぼしい商業施設はいまだにない。
一方、同じ大阪府内に造成された千里ニュータウンは鉄道に沿って一体的に開発された「線的開発」だった。そのため、線路に沿うように商業施設が並んでいる光景を見ることができる。
泉北ニュータウンの入り口となる深井駅と中心的な役割を担う泉ケ丘駅間は約4.1キロメートルもある。また、泉ケ丘駅と隣の栂・美木多駅間も約2.4キロメートル。栂・美木多駅―光明寺駅間は約1.9キロメートル離れている。
都市近郊の路線において、平均的な駅間の距離はおおよそ2キロメートル程度とされているから、これと比較すると、深井―泉ケ丘駅間は長い部類に入るだろう。こうした長い駅間距離も、「面的開発」してきたことを物語っている。
筆者は泉北ニュータウンの実情を自分の目で確かめるため、中百舌鳥駅から和泉中央駅までの全区間、直線距離にして約14.3キロメートルを実際に歩き通した経験がある。
泉北ニュータウンは起伏の激しい丘陵地に造成されているので、数字以上に駅と駅が離れている印象を受けた。
ニュータウンでの暮らし
泉北ニュータウン内に建設された集合住宅の住棟はほとんどが5階建てで、エレベーターがなかった。上層階の住民は住棟の上り下りという大変な労苦を課せられたが、加えて自宅から駅までも起伏の激しい道を歩く。そうした状況を鑑み、泉北高速の各駅にバスロータリーが整備された。
また、行政は各駅が生活拠点になるように食料品や衣料品などの日用品が購入できる大型の総合スーパーを各駅に誘致している。
さらに、1974年には泉ケ丘駅前に大型ショッピングモールが開業。その核テナントとして老舗百貨店の髙島屋を誘致した。
高島屋が店を構えたことで、泉北ニュータウンは独自の生活圏が構築され、ニュータウン内で生活が完結することも可能になった。行政の取り組みによって、普段の生活に支障が出ないように一定の配慮がされていたわけだ。
現在からすると、泉北ニュータウンの都市計画は交通アクセスに難があると感じるところだが、当時の感覚はニュータウン内で生活が賄える効率的な街と捉えられていた。
交通アクセスが後回しにされたことは、泉北高速の沿線やニュータウンを歩いていると実感できるが、新天地を求めた住民たちも入居当時は若く、階段の上り下りも起伏のある地形も苦にしなかった。
それどころか、当時は都会からは急速に自然が失われていき、工場や自動車による大気汚染・水質汚濁、振動などが公害として大きな社会問題としてクローズアップされることが多くなっていた。
1950年代から1970年代にかけて日本各地で公害が社会問題となり、特に水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく・新潟水俣病といった4大公害病や工場地帯の川崎における公害は国民に恐怖を植え付けた。そして、自然が多く残されているニュータウンに魅力を見出すような風潮が高まっていく。
革新派首長の時代
当時の世相をもっとも反映したのが政治の世界だった。なぜなら、この時期には全国で革新派と呼ばれる首長が多く誕生しているからだ。
革新派を一言で表現するのは難しいが、平たく言えば工場を誘致して経済発展を最優先するのではなく、住民の安らかな生活環境を確保することを重視する政治思想(もしくは政治家)を指す。例えば、インフラ整備においても革新派は病院や学校を優先する傾向が強い。
京都府では1950年から1978年まで7期28年にわたって革新派の蜷川虎三が知事を務め、県都の京都市においても1950年の市長選で革新派の高山義三が当選している。
もともと京都は共産党をはじめとして革新勢力が強い地域だったが、この京都をきっかけに革新派は全国へと波及していった。
1967年には東京都でも革新派の美濃部亮吉が知事に当選。以降、3期12年にわたって革新都政が続けられる。1971年には大阪府でも革新派の黒田了一が知事に当選。2期8年を務めている。
その後も、各地で続々と革新知事が誕生していく。埼玉県では1972年に畑和が、神奈川県でも1975年に長洲一二が当選した。
こうした革新の波は知事だけではなく、市民生活に近い市長職にも及んでいた。1963年には衆議院議員から転身した飛鳥田一雄が横浜市長に、1971年には伊藤三郎が川崎市長に当選している。
こうした政治の流れから読み取れるのは、有権者(一般住民)の生活が高度経済成長によって充足され、お金では買えない生活面での満足を希求するようになった、ということだ。
泉北ニュータウンは革新派の黒田知事時代ではなく、前任知事のときから計画が始まっていた。しかし、黒田知事時代に計画・造成が本格化したこともあって、生活環境を優先するという時代に適合した街になっていった。
泉北ニュータウン凋落の理由
革新という政治の流れに対して、日本人の住宅におけるマインドは簡単には変わらなかった。それが、泉北ニュータウンが凋落した一因でもある。
戦災復興期、多くの日本人は戦火で家を失っていたこともあり、行政は住宅の量を確保することを急いだ。しかし、高度経済成長期に入ると日本はマイホームを希求する声が強く、それが戸建神話へと結びついていく。
泉北ニュータウンは大阪市の住宅難を解消する目的から大量の集合住宅が整備されたが、そこから戸建へと拡大していくことはなかった。
就職したばかりの独身者や結婚した直後の夫婦なら一時的な仮住まいとして集合住宅に住むという選択肢もあるだろう。しかし、結婚して子供が増えていくことになれば話は別だ。
当時のファミリー世帯は所帯を持ったら戸建という意識が今よりも断然に強かった。集合住宅は終の住処としては相応しくない。こうした日本人のマイホームへの意識が泉北ニュータウンから転入者を遠ざけていった。
泉北ニュータウンは大阪府や住宅公団といった公的機関による集合住宅をつくる第1ステップは達成できたものの、十分な数の戸建住宅を供給するという第2ステップでつまずいたのだ。
2021年3月末時点における泉北ニュータウン内の住宅種別の割合を見ると、戸建・長屋住宅は29.5パーセントしかなく、公的賃貸住宅は46.6パーセントで約2万7700戸にも及んでいる。
老朽化によって大阪府営住宅や住宅公団の住棟の建て替えが進んだ令和においても、戸建が極端に少ない状況なのだ。昭和期の状況は推して知るべしだろう。これでは結婚を機に、もしくは子供が生まれるタイミングで泉北ニュータウン外へと転出するファミリー層が多いことも納得するだろう。
加えて泉北ニュータウンだと自宅から大阪市内の会社まで通勤すると、ドアtoドアで1時間程度を要する。東京圏なら通勤で1時間を費やすことは珍しくないが、それ以外の都市圏で通勤に1時間をかける人は多くない。
戸建住宅なら郊外に住むことを許容できても、泉北ニュータウンではそれが叶わない。こうした要因が絡み合い、新たなファミリー世帯の転入にブレーキをかけた。
その結果、街に新陳代謝が起きず、泉北ニュータウンの人口は1992年に約16万人で頭打ちとなる。
さらに泉北ニュータウンにマイナスだったのは、2000年代に東京・大阪といった大都市で都心回帰の現象が鮮明になったことだ。これによって、遠い泉北ニュータウンはますます不人気になり、それが今も続いている。
こうした状況を改善するべく、泉北ニュータウンの沿線自治体である堺市は20代30代の若いファミリー層の呼び込みに力を入れている。
かつて、謳い文句にしていた自然が豊かな点を強みとして、のびのびとした子育てができる環境をアピール。同じく沿線自治体の和泉市は大学を積極的に誘致することで若年層を引き込もうとしている。
これら若いファミリーや大学生の呼び水になりそうなのが、2025年4月1日に南海電鉄に統合されて南海泉北線となった泉北高速だろう。
これまでも南海と泉北高速は直通運転をしていたるので、大阪市まで乗り換えなしで移動できていた。ただし、これまでは泉北高速と南海を乗り継ぐため、2度の初乗り運賃を払わなければならなかった。これが統合によって初乗り運賃が1度になり、実質的に運賃の値下げにつながった。
泉北線内には泉北ライナーと呼ばれる難波駅まで座ったまま通勤できる列車が運行されている。泉北ライナーを利用するには特急料金(大人520円・小人260円)が必要になるが、運賃が値下げされたことによって泉北ライナーの利用ハードルが下がる効果が予想される。
座って通勤することを売り文句にして泉北ニュータウンへの移住を促進するトレンドが起こる可能性はある。
さらに日本人の戸建信仰が弱まっている点もプラスに作用するかもしれない。
平成半ばから、マンションのような集合住宅を好むファミリー層が増えてきた。そうしたトレンドをうまく捉えることができれば、泉北ニュータウンが巻き返すチャンスがある。
(小川裕夫)