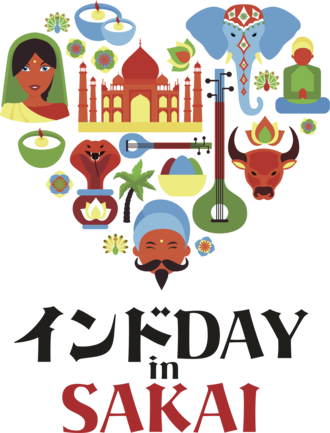江戸から大正時代にかけて現在の大阪府岬町で隆盛を極めた「谷川瓦」という瓦がある。専門家が認めたその瓦も時代の趨勢(すうせい)に従い、すでに製造が途絶えて久しいが、谷川瓦が使われていた古刹(こさつ)の本堂の葺(ふ)き替え工事を機に、その歴史と技術を後世に残そうという取り組みが同町で行われた。工事を通じ、谷川瓦について少しでも知ってもらえればと関係者は話す。
工事が行われたのは平安時代創建とされる興善寺(同町)。天台宗の最高位、天台座主にもなった円仁が創建したと伝わる寺院で、1570年頃に戦災で焼失したが、江戸時代の1690年頃に再建され、その際、重要文化財のある本堂の屋根はすべて谷川瓦が使われたとみられる。全面的な葺き替えは、この再建以降初めてとなる。
谷川瓦は和歌山県岩出市の根来寺には現存最古の1515年作と伝わるものがあるほか、先の大戦で焼失した和歌山城にも使用されるほどの人気で模造品が出回ったことも。品質を守ろうと明治22年には製造業者らが会社を組織し、商標登録も行った。
しかし昭和に入ると大量生産の瓦に押されたうえに、先の大戦で、原料の土のある山が削られ、周辺は空襲にも見舞われた。戦後は燃料や原料が不足、排煙が問題となったこともあり衰退していったという。

工事に関わった元和歌山県文化財センター職員で、文化財建造物保存修理技術者の鳴海祥博(よしひろ)さん(75)は谷川瓦の特徴を「薄いのに強度があり文様も洗練されている」と説明する。興善寺本堂の屋根にはずれ落ちないように形に工夫を凝らした瓦もあった。