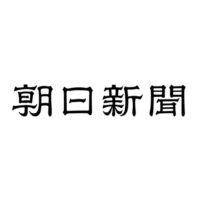全国各地のショッピングモールを巡り、そこから見えてくる都市の「いま」をお届けする本企画。今回は「だんじり祭」で有名な、大阪府岸和田市に来ています。
岸和田の海沿いに建つ「岸和田カンカンベイサイドモール」がなんとも寂しい状況になっている……という話が耳に入ったのです。
現地はどのようになっているのでしょうか? 調査で見えてきたのは、たしかに寂しい現状と、全国のショッピングモールを活用する「思わぬ方法」でした。
岸和田カンカンに行ってみた
「岸和田カンカンベイサイドモール」(以下、岸和田カンカン)は南海電鉄南海本線の岸和田駅から徒歩10分ほどのところにあります。
駅前から続く商店街を抜けて少し歩くと、大きな長方形の建物が目に入ります。これが、岸和田カンカンです。
まずは基本情報を見てみましょう。
所在地:大阪府岸和田市港緑町2-1
敷地面積:約3万6460平米
開業年月:EAST館…1997年3月、WEST館…1999年9月
駐車台数:約2000台
アクセス:
南海電気鉄道南海本線岸和田駅から徒歩約10分
阪神高速湾線岸和田南ICから約1分
ちなみに、一説によると「カンカン」という施設名は岸和田だんじり祭の見所の1つである「カンカン場」から来ているとのことです。
ショッピングモールはEAST館とWEST館に分かれています。EAST館は大きなスーパーマーケットのようなハコ形の建物で、デザインも控えめです。
一方、WEST館は、建物全体の形も半円形のようになっているなど、ヨーロッパを思わせる非日常的なデザインです。
普段使いができるEAST館
建物の雰囲気から異なる、EAST館とWEST館。その内装や機能にも違いがあるのでしょうか。まずはEAST館に入ってみます。
館内には若年層を中心にそこそこの人がいます。テーブルと椅子がたくさん置いてある「コミュニティスクエア」には、多くの人が集っていました。
それもそのはず。EAST館は「ミスタードーナツ」「Seria」「しまむら」など、人気チェーン店が入っているのです。日常使いに便利で、中高生たちが自転車などを使ってちょっと遊びに出かける……という時にも重宝しているのでしょう。
一方で気になる点もあります。いくつかの区画ではテナントが抜け、寂しい雰囲気になっている点です。
EAST館の核テナントであったスーパーの「ラ・ムー」の完全撤退でシャッターが降りている状況も、その雰囲気に拍車をかけていました。
実は岸和田カンカンの前には、極めて巨大な「コープ岸和田店」があり、道路を挟んでスーパーが2つある状態でした。ラ・ムーは苦戦を強いられていたのでしょう。
なお、このコープには、「DAISO」や「サンドラッグ」といったEAST館内と競合するテナントも入っていました。
ラ・ムーの跡地には、近年勢力を拡大しつつあるスーパー「ロピア」が6月下旬に入居する予定です。ロピアは2020年から関西に進出しており、どの店舗も盛況。今後は、岸和田の地でコープとロピアの戦いが始まりそうです。
それ以外の多くの空き区画にもオープン予定店舗の案内が貼られており、入居する側は、工夫さえあれば集客が可能な場所だと思っているのではないでしょうか。
そういった意味でも、ほかの「廃墟モール」とは一線を画していると言えます。
人がいないWEST館
EAST館に比べて厳しい状況なのがWEST館です。EAST館がすべて屋内店舗なのに対し、こちらは一部、屋外店舗もあります。
WEST館を歩いてみても……なかなか人に出会いません。
実際かなりの区画が空いてしまっています。また、「ガラガラモール」にありがちな「とりあえず空き区画をパネル展示やゲーム機で埋めておく」といった場所も多く、かなりの苦戦ぶりが窺えます。
この建物は「イギリスの伝統ある港町」をモチーフにしているそうで、建物自体は立派です。しかし、そこに誰もいないので、豪華な建物がかえって虚しく映ります。
そもそも、WEST館は「アウトレットモール」として開業した経緯や、敷地内のやや奥まった場所にあるという状況があります。
EAST館のほうが、スーパーのような日常使いできるテナントが多く、位置的にも客やテナントが入りやすいといった事情があると思われます。
用途が混在した施設構成が裏目に?
1997年に開業した岸和田カンカンは、岸和田市、大阪府、民間企業が手を組んで行った岸和田旧港地区再開発事業の一環として作られました。「アクアヴェルデ岸和田」というまちの一角を担っています。
最初にEAST館が開業し、その2年後に、港沿いでリゾート気分になれるアウトレットモールとしてWEST館がオープンしました。
日本初・関西初のテナントを多く取り揃えた岸和田カンカンには、開業当初1カ月で120万人の来場者があったといいます。予定は100万人だったので、それを20万人も上回る数値です(一般社団法人日本ショッピングセンター協会:「ショッピングセンター 」1999年12月号)。
しかし、関西圏には同時期に複数のアウトレットモールが誕生します。中でも2000年に誕生した「りんくうプレミアム・アウトレット」は現在も多くの客を抱える一大アウトレットモールです。
上記を含む数々のアウトレットモールとの競争の中で、岸和田カンカンは次第に衰退。現在のWEST館のような状況になってしまったわけです。
そもそも岸和田カンカンは、ほかのアウトレットモールに比べると「中途半端」でした。
開業当初の資料によれば「岸和田カンカンはデイリーニーズの高いEAST館(スーパーと専門店)と非日常的な空間のベイサイドモールを持つ」と紹介されています。
つまり、当初から「日常使い」と「観光向け」の両面が同居するという、いわゆる「ハレ」と「ケ」を併せ持つ設定だったのです。
この設定は、一見するとさまざまなニーズを満たせる良い案にも思えますが、かえって中途半端になってしまいました。
例えば、競合であるりんくうプレミアム・アウトレットと比べた場合、店舗面積、店舗数、駐車場台数など施設規模において勝る要素がありません。こうなると、利用客はわずか10キロメートル程度しか離れていないりんくうプレミアム・アウトレットに行くことを選ぶでしょう。
用途が混在した施設構成が、岸和田カンカンWEST館の運命を決めてしまったように思います。
映画館とスポーツアクティビティで集客を狙う
とはいえ、岸和田カンカンのWEST館は、これまで本連載で取り上げた「大洗SEASIDE STATION」(茨城県)や「カリヨン広場」(兵庫県)のように、完全に人がおらず、回復する見込みもない、という感じではありません。
歩いていると、ちらほら目に付く小学生や中高生の姿。春休みだったこともあるのでしょうが、数は少ないながらも、人がいるにはいる状況でした。
その理由の1つが、映画館です。WEST館の3階には岸和田市唯一のシネコン「ユナイテッド・シネマ岸和田」があります。開業当初から設置されており、当時は「関西最大級」のシネコンとして話題を集めたようです。
さまざまなショッピングモールを回ってきた筆者は、やはり映画館が併設されているモールは、併設されていないモールに比べて高い優位性があると実感しています。
すでに本連載でもお伝えしたように、ショッピングモール・センターの数は、2018年を境に減少傾向にあります。全国各地で多くの商業施設が作られ、それらが食い合いを起こしているからです。
必然的にショッピングモールの自然淘汰が起こるのですが、「映画館の有無」は集客を左右する大きな役割を果たす要素です。
日本映画製作者連盟の「日本映画産業統計」を見ると、2024年は映画館に1億4400万以上の入場があり、映画は大きなエンターテイメント事業と言えます。
特に地方は映画館が少ないため、映画館のあるモールには人が集まる傾向があります。
先にも述べたように、WEST館のシネコンは岸和田市内唯一ですので、モールへの誘動材料になるのは間違いありません。筆者がWEST館で見かけた中高生たちも、映画を見た後に集まっていたのかもしれません。
また、親子連れの姿も見かけました。その背景には、建物の中に子ども向け施設が多く含まれていることがあります。
例えば「あみあみカンカン」。これは、WEST館のトレードマークである中央の塔内に設置されている、ネットを使ったアスレチックアトラクションです。
ホームページによれば、このアクティビティの商業施設内の設置は関西で初めて。子どもも大人も一緒に遊べる遊具で、訪問時には何組かの親子が遊ぶ姿を見ることができました。
そのほか、いろいろな生物に触れて楽しめる「いきもの探検隊」、WEST館前の中央広場にそびえるクライミングウォール「カンカンウォール」にも子どもが集まっていました。
幅8メートル、高さ15メートル、最大斜度135度の国際基準を満たしたクライミングウォール(引用:岸和田カンカンベイサイドモール)
特に「あみあみカンカン」や「カンカンウォール」といった、スポーツアクティビティを積極的に設置することで、ほかのモールとの差別化を図ろうとしている様子が窺えます。
「ガラガラモール」の新たな活用方法
WEST館に集まる人たちを見ていて、面白い発見をしました。
前述の通り、WEST館の広場は基本的にがらんとしているのですが、そこで「TikTok」の撮影をしている女子学生グループが何組かいたのです。映画を観に来た帰りなのでしょうか。
TikTok内の人気コンテンツの1つに「ダンス動画」があります。学校などで撮影されているものも多いのですが、WEST館のように人の目を気にする必要がないショッピングセンター・モールは、撮影場所としてうってつけなのかもしれません。
敷地内で鬼ごっこをして遊んでいる子どももいました。ある意味、人の少ないショッピングモールがまるで「空き地」のように自由に使われている状況を発見したのです。
このような光景が見られるのは、WEST館が屋外にある、駅から徒歩圏内の立地、映画館など子どもが集まりやすい施設がある、といった要素があってこそなのでしょう。
つまり、すべての「ガラガラモール」でこういった風景が望めるわけではありません。ただ、こうした子どもたちの様子から、今後日本各地に増えていくであろうモールの1つの姿が見える気がしました。
工学者・都市計画家の饗庭伸氏は自著『都市をたたむ』の中で、人口減少によって全国に空き家が増える時代において、新築を増やしていくのではなく、それらをいかに活用していくのかの重要性を説いています。
それは、空き家だけに限らず、ショッピングモールのような商業施設も同様でしょう。
本連載でも、ショッピングモールの飽和状態により、全国に空きテナントだらけのモールが増えていることは述べた通りです。
以前の連載で紹介した「ポレポレシティ」(茨城県)のように、行政とイオンが組んで子どものための広場を作るといった例もあります。
この取り組みは大人が考えた「ショッピングモールの使い方」ですが、子どもがこうした発想を超える自由な使い方をしていたり、今後新しい使い方を生み出したりするかもしれません。
そして自然に発生した子どもの「空き地」的利用方法に注目すると、活用のさらなるヒントになる気がします。
ショッピングモールで見られる何気ない風景にこそ、その未来の姿が隠れているのかもしれない、と思った調査でした。