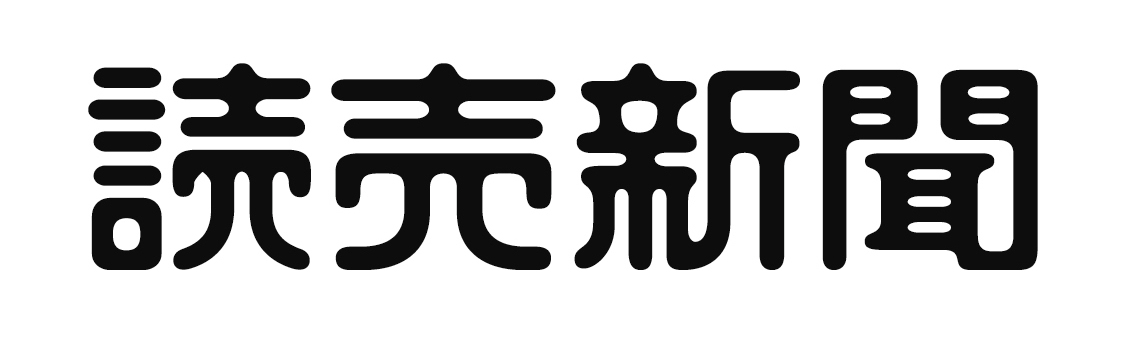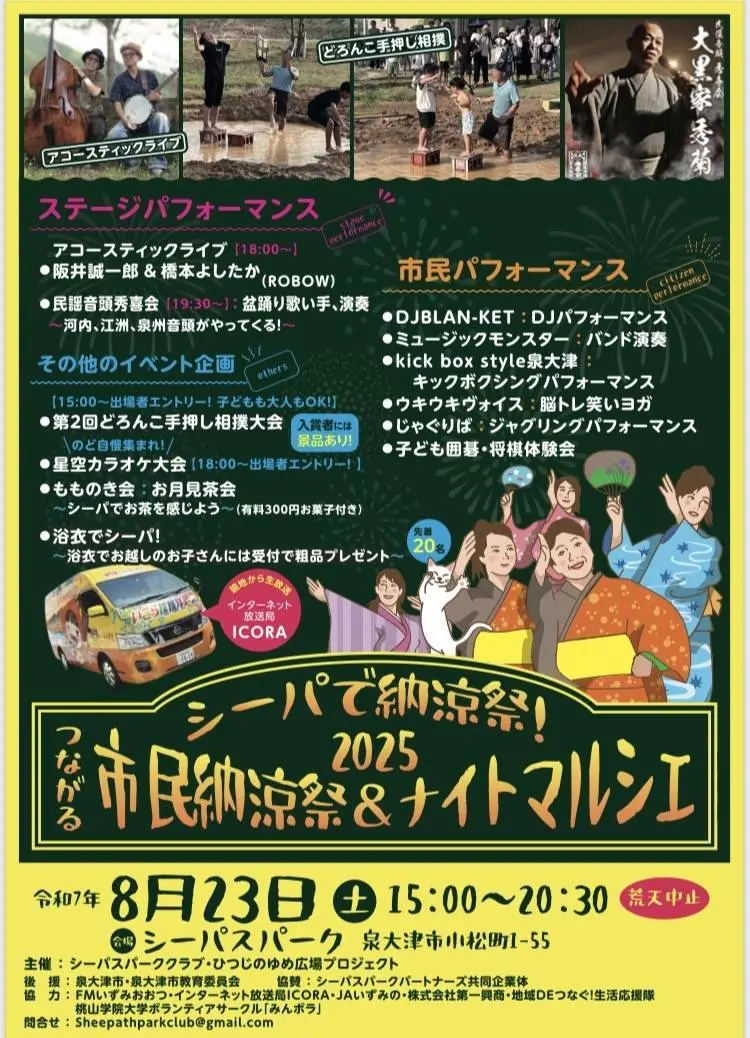北前船に関連する文化財が残る泉佐野市に、ゆかりのある16道府県52市町の名所などが描かれた壁画が登場した。北海道から泉佐野市まで、北前船がたどった寄港地の文物を表現。市は、文化財がある中心市街地への誘客につなげようと、SNS発信に力を入れている。(門間圭祐)
北前船は江戸から明治期にかけ、瀬戸内海から日本海に出て、大阪と北海道を往来した商船。寄港地や船主集落では、広大な商家や蔵が立ちならび、民謡など各地の芸能が船乗りたちによって伝わったことで交易に加え、文化的な交流も活発だった。
文化庁は、泉佐野市など16道府県52市町を日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」として認定している。
壁画は市立佐野中学校の塀(全長約170メートル)に描かれた。市がゆかりの歴史文化などを壁画で紹介することを着想。東京を拠点に壁画制作を行っている加藤文子さん(42)らにデザインを依頼した。
北前船の航路をたどるように、泉佐野市から北海道までの名所や祭礼などを航路順に紹介している。
泉佐野市には「佐野浦」と呼ばれた海側エリアに米や綿花栽培に用いる肥料など各地の産物が運ばれ、北前船は綿製品やたばこなどを積み込んで北海道に向かった。井原西鶴の「日本永代蔵」(1688年)に登場する食野家や唐金家などの回船問屋などが巨万の富を築き、海岸一帯には蔵群が立ち並んだ。
現在でも同エリアには、細い路地が縫うように張り巡らされ、往時をしのぶ蔵や豪商の 菩提 寺などが現存している。
壁画では、食野家の菩提寺「西法寺」の建物や漁業の安全と大漁を願って営まれる「ふとん太鼓祭り」のにぎやかな風景が楽しめる。
そのほか、「風待ちの港」の特徴である、いり組んだ深い入り江が現存する島根県浜田市の外ノ浦の街並みや、舌を出した男の図柄が目を引く秋田県能代市の「能代 凧 」など日本海側の市町の歴史や文化を鑑賞できる。
3月12日には、同校の美術部員や夜間学級の生徒ら約20人が壁画制作に参加。生徒らは、加藤さんの指示を受けながら、塀に何色ものペンキを丁寧に塗っていた。
加藤さんは「北前船で栄えた歴史は街の資産。街の価値を認識してもらうきっかけにしたい」と述べ、同校の中学3年大北明香里さん(14)は「壁画を制作するなかで、泉佐野の北前船の歴史を知ることができた。後輩たちにも知ってもらいたい」と話していた。
大阪・関西万博の開幕で外国人を中心に府内で観光客の増加が見込まれており、市は今後、SNS発信やチラシの配布などでPRする予定だ。中岡勝・市文化財保護課長は「日本遺産に訪れてもらう看板のような存在になってほしい」と期待を寄せている。