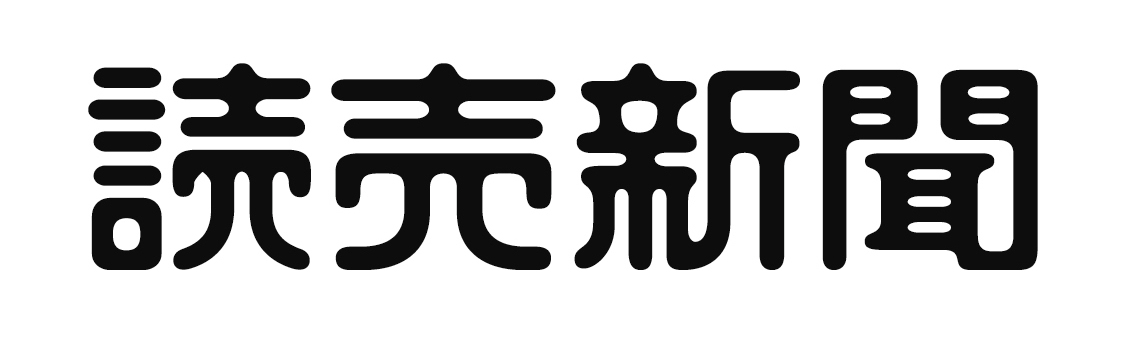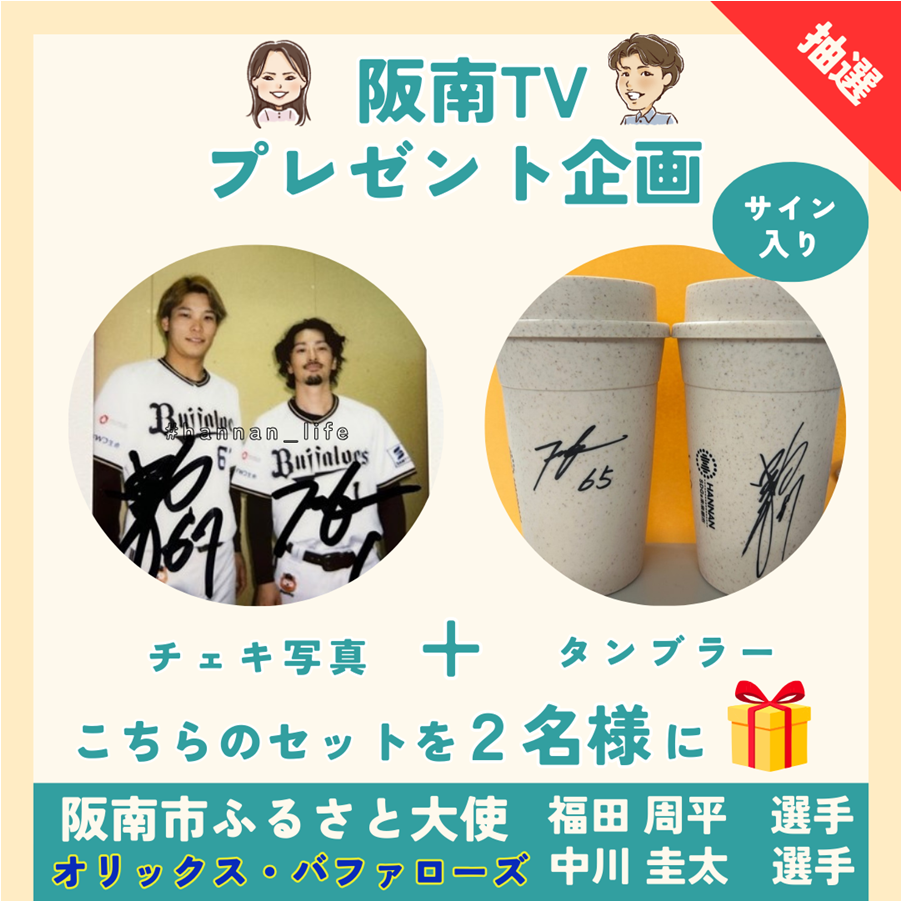「包丁」「和菓子」「注染・和晒(わざらし)」「昆布」「線香」など堺の伝統産業を紹介している施設が『堺伝匠館』だ。フランス人が《案内人》を務めているというので、堺観光ボランティア協会の川上由広報部長と一緒に訪ねた。その伝匠館の展示で、前述の伝統産業品以外で新たな発見をした。「堺五月鯉幟(こいのぼり)」。真鯉(まごい)の背に金太郎が乗っている。川上部長によれば「堺ではすべて乗っています」という。さらにすべて手描き。端午の節句(5月5日)も近づいている。さっそく工房へ!
一枚一枚手描き
堺五月鯉幟の工房「高儀」は堺市西区浜寺船尾町にある。大阪府内唯一の手描きこいのぼり工房だ。
3月中旬に訪ねた。「むさ苦しいところですが」と笑顔で迎えてくれたのが、経営者で伝統工芸士の高田武史さん(70)。工房に入ると部屋中に制作途中のこいのぼりが何十本もつるされている。
「しまった」と思った。こいのぼりは5月の縁起物。一枚一枚、手描きの「堺五月鯉幟」はいまが一年中で最も忙しい時期。取材とはいえ筆者と話している時間も惜しいはずなのだ。
訪問したときはちょうど鯉のうろこに薄墨を入れるところ。高田さんによれば、1枚を一気に仕上げるのでなく、目なら目、金太郎なら金太郎―と日を分けて描き上げていくという。
「父は工房を見せることに大反対やったんですよ」と高田さんははけを動かしながら話してくれた。
「ここを見せ物小屋にする気か!とえらい怒られましたわ。でもね、手描きのこいのぼりや―というても、買ってくれる人には、ほんまに手描きかプリントなんか分かりません。だから、ちゃんと描くところを見せなあかん―と父を説得したんです」
「堺五月鯉幟」は明治初期、玩具商を営んでいた初代高田儀三郎氏が名古屋の紙鯉をヒントに勝間凧(こつまたこ=和凧)職人に紙鯉を作らせて販売したのが始まり。屋号の『高儀』は初代の名前から取ったもので創業は明治元年。実に157年の歴史がある。武史さんは6代目。
最大の特徴は真鯉の背中に金太郎が乗っている図柄だ。大正時代に音吉という職人が考案したと伝えられており、足の人さし指が親指より長く描かれている。「親を超えていけるように」という願いが込められている。そして同じ幅の筒状ではなく、本物の鯉のように胴が太くふっくらしているのも特徴。
「鯉のひげも見てください。ひげが前にはねているでしょう。前はねのひげで高儀の鯉だと分かるんです」と武史さん。
それにしても見事なものだ。どのこいのぼりも金太郎の顔やポーズは同じ。下書きもなく何十種類のはけと筆で一気に描き上げたもの。言葉は悪いが、まるでプリントしたかのようだ。
「それは褒め言葉です。美術の絵画ではないので個性はいらない。同じ物を丁寧に同じように描くことが大事なんです」と武史さんは笑った。それが伝統工芸士の「心」なのだろう。
最後に気になったことを質問した。「7代目は?」。武史さんは小さな声で「娘が継いでくれました」とポツリ。奈良芸術短大で日本画を学んだ恵(めぐみ)さんが、父の武史さんとこの工房を支えている。
府内で1軒しか手がけていない手描きのこいのぼり。その希少価値が認められ、いまでは海外からも多くの注文が来る。だが、そうなるまでには何度も廃業の危機があったという。時代が変わっても親が子を思う心は同じ。ことしも「堺五月鯉幟」が大空を泳ぐ。
海外では置物が人気
高田武史さんによれば「エリックさんの推薦のおかげで、海外からの注文が多くなった」という。といっても海外で5月にこいのぼりを揚げる習慣はない。壁に飾る「タペストリー」や「タオル」、小さなこいのぼりの置物が人気という。
もちろん、置物といってもすべて手描き。最大9メートルのこいのぼりも置物も、手間ひまは同じなのだ。
「日本でもこいのぼりを揚げる家庭は少なくなりましたね」と高田さんは少しさびしそう。「大阪の伝統産業」を守るためにも、大阪府の各官庁や学校が率先してこいのぼりを揚げる。いいと思うんだがなぁ。
熱意のフランス人案内人
『堺伝匠館』の《案内人》を務めるのはフランス人のエリック・シュヴァリエさん(35)。まげのように髪を後ろで結び、黒の作務衣(さむえ)姿が格好いい。フランス語をはじめ英語、中国語、韓国語はもちろん、流暢(りゅうちょう)できれいな日本語を操る。
「江戸時代、生魚は腐りやすくなかなか食べられなかった。でも、堺の包丁職人が片刃包丁を発明したことで、生魚が切りやすい、菌がつきにくい、腐りにくい状況になった。わたしたちがお刺し身やおすしを食べられるのも、堺の包丁職人のおかげかもしれません」
エリックさんの説明は説得力がある。それもそのはず、堺でも有名な老舗の鋏(はさみ)・包丁鍛冶「佐助」で5年間修業し、専門的な知識は豊富。といっても「包丁職人」になろうとしたわけではないという。
「17歳のときに日本語を聞き、なんてきれいな言葉なんだと思い、フランスの大学で日本語を学びました」というエリックさんは日本語を勉強するために平成24年1月に来日。そのときに知り合ったのが「佐助」の5代目当主、平川康弘さんだった。
エリックさんは平川氏から「フランス人の弟子募集」のチラシを作って―と頼まれ、フランスで募集したが応募なし。じゃあ、エリックさんがやる? そんな流れで「佐助」に弟子入りしたという。
「職人よりも、これまでの経験と知識を生かして多くの人に堺の伝統産業の素晴らしさを伝えたい」
エリックさんの正式な肩書は「堺市産業振興センター」の海外販路開拓コーディネーター。ネットや交流サイト(SNS)を使って世界に「堺の包丁」の魅力を発信している。
そのおかげか、これまでのお土産としての包丁ではなく、プロの料理人が使う包丁として世界各国のバイヤーが買い付けに来るようになった。「堺伝匠館」の年間売上額は令和5年度に1億円を超え、年々売り上げを伸ばす勢いという。(田所龍一)