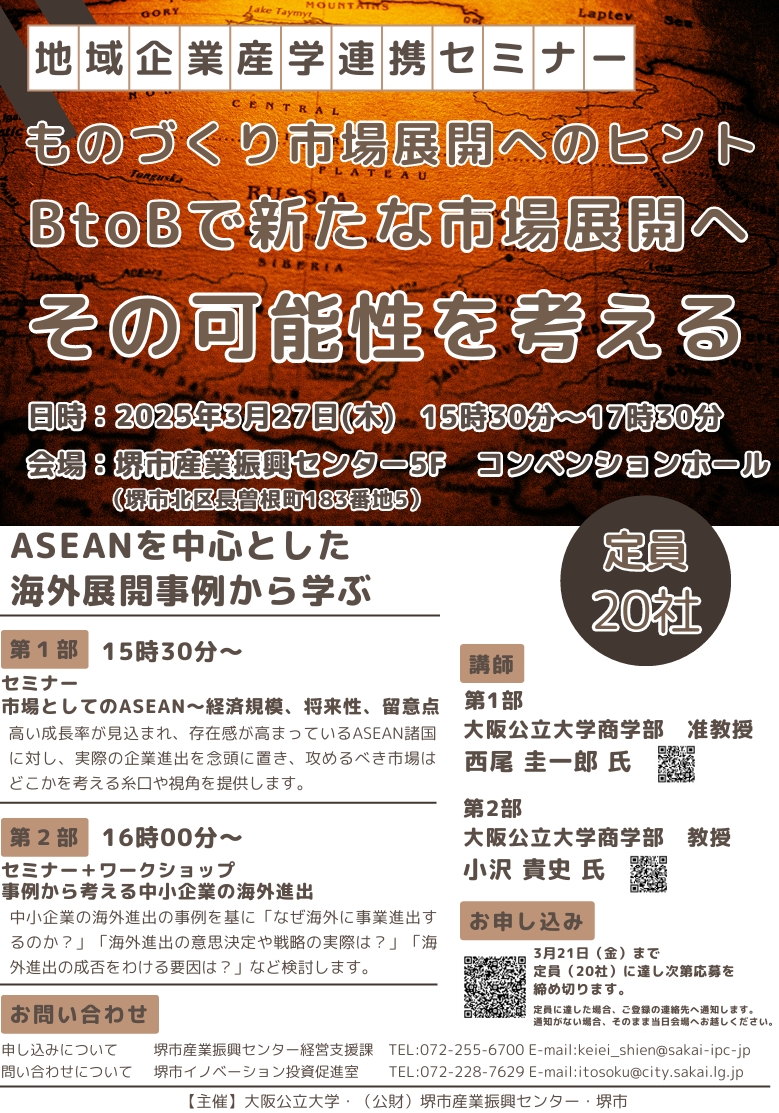堺市の広報担当や観光ボランティアのみなさんたちが「ぜひぜひ一度、会ってみて!」と力説する人物がいる。その人物とは、堺市博物館で学芸員を務める矢内一磨(やないかずま)さん(60)という。なんでそんなにみんなが推薦するのだろう…と思いながら博物館を訪ねた。
映画の役モデル
堺市博物館は仁徳天皇陵の真向かいの大仙公園の中にある。最寄りの駅はJR阪和線百舌鳥駅から500メートル。堺市制90周年を記念して昭和55年に建てられた博物館だ。南海高野線の堺東駅からバスも出ている。
「ようこそ、いらっしゃいました」と矢内さんは両手を広げて笑顔で出迎えてくれた。ブルーのワイシャツに紺のベスト。小太りでやや短足。人をひきつけるような無邪気な笑顔。そしてしゃべり出すともう止まらない。説明というよりも「詩」を語っているように気持ちよさそうに話す。実はあの映画に出てきた「あの人」のモデルになっている。
あの映画とは平成30年1月5日に公開された千利休の《幻の茶器》をテーマにしたコメディー『嘘八百』。中井貴一扮(ふん)するしがない目利きの古物商と落ちぶれた陶芸家(佐々木蔵之介)が手を組み、利休の幻の茶器「大海原」をでっち上げて、昔、痛い目にあわされた有名古美術鑑定士(近藤正臣)をだまして仕返しするという物語だ。
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/EAKNW7VZTRL47EFQKPBBMBVY7A.jpg)
監督は28年に『百円の恋』で第39回日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞した武正晴氏。脚本は堺市出身で「堺親善大使」を務める今井雅子さんと足立紳氏。オール堺ロケで製作された。お笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅が扮する博物館の学芸員・田中四郎(利休の幼名、田中与四郎からとっている)のモデルとなったのが矢内さんなのだ。
/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/6YSUZBHPA5PITPWP6AESBLH7OY.jpg)
脚本を急遽変更
「いやぁ、あれは武監督が突然、思いつかれて…」と矢内さんは照れてみせた。当初の脚本では「田中学芸員」は登場しない。製作前に「利休」のことを調べに武監督と今井さんや製作スタッフが堺市博物館を訪れたときのこと。
「利休はね、昔《かもめ》というあだ名があったんですよ。自由気ままに、かもめのように生きる利休をそう呼んでいた―と茶人・津田宗及の息子の江月宗玩の語録集『欠伸稿』の中に書かれています」
「あそこの夕日も利休が見たんでしょうなぁ。この空も…」
手を後ろに組んで窓の外を見上げながら滔々(とうとう)と話す矢内さんに武監督は感動した。武氏は当時の思いを30年の雑誌「シナリオ」2月号でこう語っている。
「すごくロマンチックな人。矢内さんのしゃべっていることは難しくて分からないけれど、とにかく本人は夢中になってしゃべっている。こういう人が(映画に)出てきたら面白いなと思ったんです」
矢内さんもいう。
「ボクが説明しているとき、監督さんだけ席を離れて、いろんな角度からボクを見ているんです。変な人だな―と思っていました。あとで聞くとボクをどう撮るか探っていたとか。映画監督って変わってますね」
武監督はその日の帰りに今井さんへ「あの人を映画に入れよう」と脚本の書き直しを指示した。そして矢内さんに風貌が似ているお笑い芸人の塚地武雅氏を起用。塚地氏には髪形から服装、しゃべり方、表情の作り方など徹底的に矢内さんに似させるように指示したのである。
「ボクはきっと佐々木(蔵之介)さんが学芸員役をやってくれると思っていたんですが…」と矢内さん。矢内さんのすごさはもう一つ。この物語でポイントとなる切腹直前に書いた「利休の譲り状」。紙の大きさや折り方をスタッフに伝授。そして「当時の手紙には必ず和歌が添えられているものです」と今井さんにアドバイス。「私にはそんな和歌はつくれませんよ」と困る今井さんに「では、ボクが…」と作ったのがこの和歌だ。
《きょう落つる 露ひとしづく 和泉の津 わたのはらにて 一人遊ばむ》
お見事!
矢内さんってどんな人?
会う前に堺市の関係者に言われたのは「一を聞くと十倍になって返ってきますから気をつけて」というもの。とにかく話し出したら止まらないのだ。
「ついつい夢中になって…。観光ボランティアの人たちも、ボクが話し始めると、仕事がありますから、このへんでぇーと逃げて行っちゃうんです。今では《天敵》扱いです」
いやいや、観ボラさんだけではない。なんと矢内さんの奥さんもその一人。きっと家に帰ってもしゃべり続けたのだろう。「これからは、これを私だと思って、これに話しかけてくださいな」とゾウのぬいぐるみを渡したという。
矢内さんは兵庫県たつの市で生まれ、育ったのは同県加古川市。「ボクの名前(一磨)の磨は播磨から取ったんです」。平成4年、同志社大学大学院文学研究科文化史学専攻、博士課程研究指導修了のれっきとした文化史学博士。古文書を研究し『一休派の結衆と史的展開の研究』(思文閣出版=22年)で博士号を取得している。「祖父や父が堺市で教師をしていたんですよ。だから堺とは縁があります」。
『嘘八百』の第1弾が終わったあと、堺市が製作した「ロケ地マップ」を手に自らガイドを務めたという。堺市博物館、さかい利晶の杜へ行ったなら、ぜひ「矢内さんいますかぁ?」とたずねてみましょう。(田所龍一)