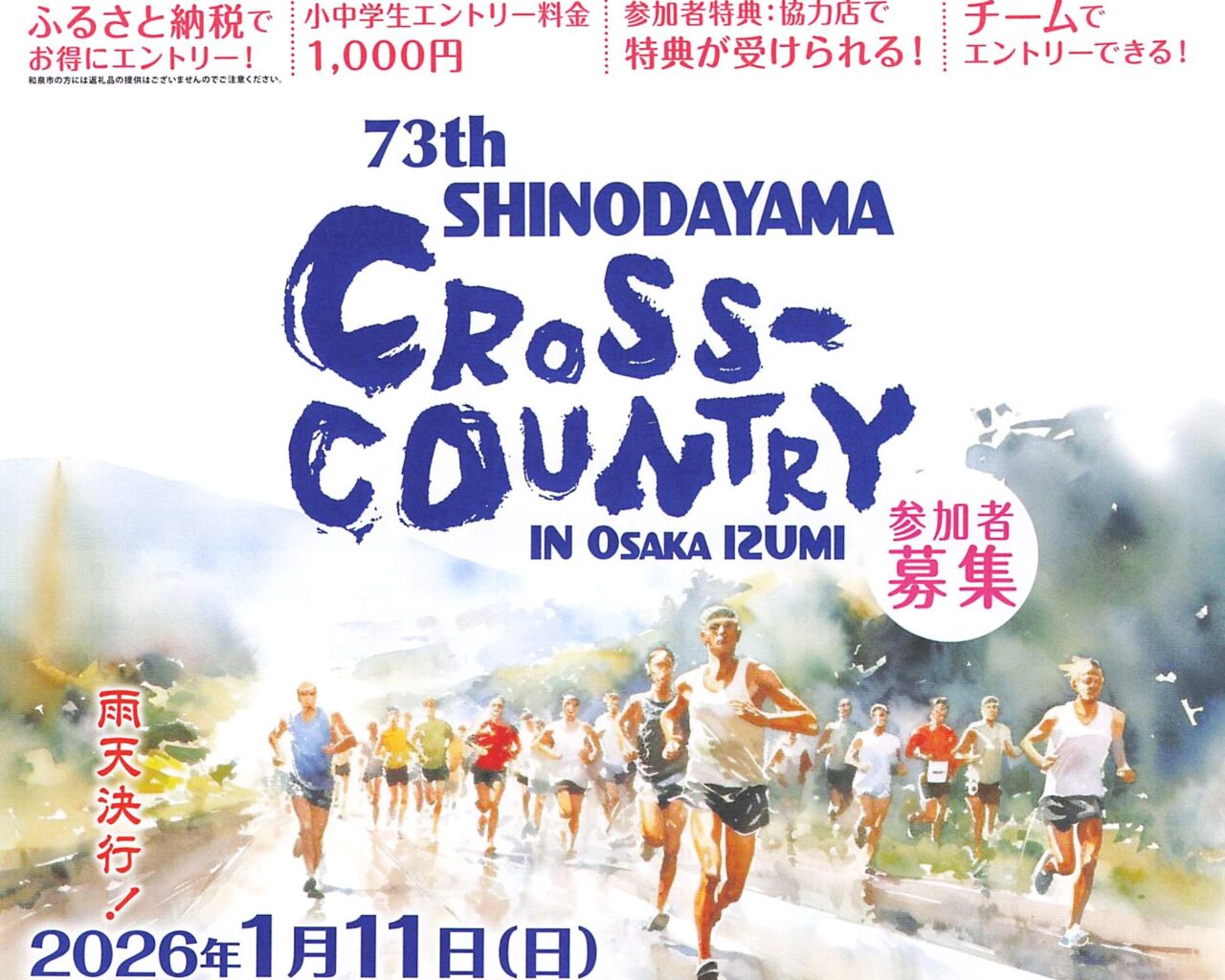近代ガラスの製造技術が日本に伝わったのは19世紀後半。20世紀初頭には国内でも技術が確立し、多くのガラス製品が生まれるようになった。その中でも、“軟質”という特性をもつ独特な伝統工芸品「いずみガラス」は、丸みを帯びた温かみのある風合いが特徴だ。
今回は、そのいずみガラスを戦前から製作し続ける唯一の工房、佐竹ガラスを訪ね、代表である佐竹保彦さんにお話を伺った。
1946年大阪和泉市に生まれ、鉄工関連の仕事に携わっていたが、当時の社長(父)の死去に伴い事業(ガラス工場)を引継ぐ流れとなった。ガラスに関しては全くの無知であり、長年勤めていただいていた職人さん達のサポートにより、短期間で一から学ぶ事が出来た。その中でも最初に言われた事は弊社の社是にもしている「品質は会社の未来を左右する」と言う事でした。品質と言う言葉には奥深い意味があると今なお感じられます。
人造真珠の8割を製造 和泉の地を支えた手仕事とは
この町には、かつて人造真珠の文化が根付いていたそうですね。
ええ。人造真珠は大正時代から作られており、最盛期には日本のGDPの1割近くを占めていた、なんて話もあります。その約8割が、この和泉市で生産されていました。
私が知っている昭和20〜30年代のこの地域では、中卒、無給での弟子入りが当たり前でした。
でもみんな頑張っていましたよ。なぜかというと、人造真珠作りは当時のサラリーマンの10倍くらい稼げたんです。そして、腕のある人なら3か月ほどで仕事を覚えられました。
鉄からガラス、そして色ガラスの世界へ
佐竹ガラスの創業について教えてください。
創業は1927年。当初は鉄工所だったのですが、先代が亡くなったのをきっかけにガラス製造に転向したのです。
最初は人工真珠用の乳白のガラス棒を作っていましたが、アメリカのバイヤーの要望で色のついた色ガラスが求められたことで、色ガラスの製造を手がけるようになりました。そして現在は、色ガラス製品の素材となる色ガラス棒やいずみガラス製品の製作を行っています。
素材や製法には、どんな特徴があるのでしょうか。
使っている主原料は創業当時から変わらずオーストラリア産のけい砂等です。
純度が高く、不純物が少ないため、発色が非常に美しい。
鉛ガラスとソーダガラス、どちらも扱っていて、色に応じて使い分けます。赤やオレンジなどの暖色系はソーダガラスでなければ出ないんです。
作業は今も基本的に手作業ですね。ガラスは坩堝(るつぼ)という容器で溶かして作ります。そのため色ごとに坩堝を変える必要があるんです。
通常のガラスなら坩堝は一つで済むので機械化が可能です。しかし色ガラスはそうはいかず、手作業の方が効率がいいという逆転現象が起きています。
ただ溶解炉の燃料だけは時代と共に変わり、木から石炭、油、ガスと移り変わっていますね。
戦後、この地域には同じような工場が20社以上ありましたが、今では私たちを含めて2社だけになりました。戦前から続いているのは、弊社だけですね。
「ガラスが好きなわけじゃない。でも性に合っていた」
現在の佐竹ガラスの取り組み状況を教えてください。
今は個人のお客様が中心です。以前は企業向けに大量生産していましたが、人工真珠の素材は次第にプラスチックや貝に置き換わっていきました。代わりに増えたのが個人需要です。
というのも、20数年前から「とんぼ玉」を趣味で作る方が増えてきたのです。とんぼ玉は比較的作りやすく、高値で販売できる。こうした理由からとんぼ玉を作る方が増え、その素材となる色ガラス棒の需要が高まりました。
私たちの視点では、少量多品種となってしまったので、昔と比べ生産効率が落ちているという事実はあります。ただ求められるものに応えるのが私たちの役割だと感じています。
今後は、いずみガラスの特徴である軟質を生かした製品開発や、業務用途への展開など、事業を安定させる新しい挑戦を進めて行きたいと思っていますね。
長年、色ガラス作りに携わり続けてきた佐竹さんにとって、ガラスとはどのような存在なのでしょう?
正直に言うと別にガラスが好きだったわけではないんです。もともと鉄の仕事をしていた人間ですから。
でも、気づけばガラス製品を作り続けて45年。好きとか嫌いとかではなくて、自分のやるべきこととして、ガラスと向き合ってきました。
続けてこられたのは、色ガラス作りが性に合っていたからでしょうね。
私には職人として「お客さんの期待に応えたい」という気持ちがあった。だからこそ、目の前の一本一本に向き合う原動力となっていました。
結果として、それが今につながっているんだと思います。
今でもガラスに対して「ああ、綺麗やな」と思うこともありますよ。よくガラスは「シースルーが特徴だ」なんて言われますが、それだけならプラスチックでも同じことが言えます。でもガラスには復元力がある。
プラスチックは経年でくすみが出ます。しかし、ガラスは水で洗えば、新品同様に輝く。その強さ、美しさといった魅力を見つけられたのは、長く携わってきたからこそでしょう。
触れたからこそわかる先人の知恵
職人の数は今、どのくらいですか?
多くはないですが、やってみたいと言って入ってくる若者はいます。そのなかでも金銭目的ではなく、“好きだから”という理由の人は続きますね。ガラス棒作りは、勘が良ければ3年、普通でも5年あれば一通りの技術が身につきます。
海外からの注文もあるのでしょうか?
はい。特に韓国からの問い合わせが多いですね。派手な色よりも、落ち着いたトーンが好まれます。そういう意味では、日本的な色合いが再評価されているのかもしれません。
近年、海外のお客様や若い世代の方々が歴史ある文化財や当社の軟質ガラスに興味をお持ちいただき工場見学やとんぼ玉製作体験にお越しになられております。
その他にも公共的な団体からの依頼を受け、古代ガラスの復元や城郭・寺社仏閣等の文化財修復にも携わっております。
何百年も前の建物に触れると、先人の知恵に驚かされます。例えば、線一本のねじりだけで強固な構造が成り立っていて……。ああいう発想や感性は、今ではなかなか出てこない工夫だと思います。
だからこそ、伝統は続けていかなければいけないと感じるのです。先人が積み上げてきたものを、次の世代に渡していく。
これからも、職人としてその役割を果たしていきたいと思います。