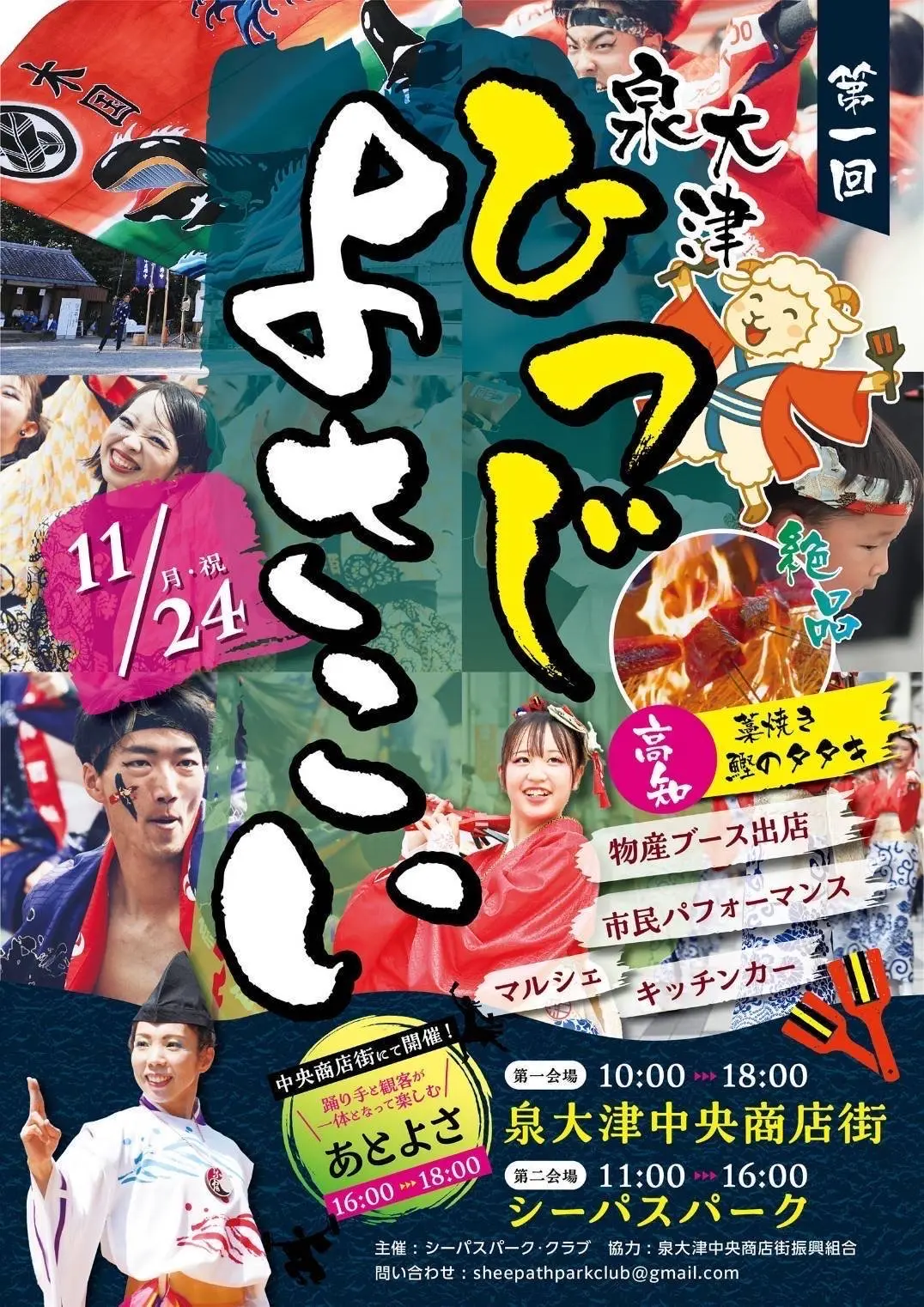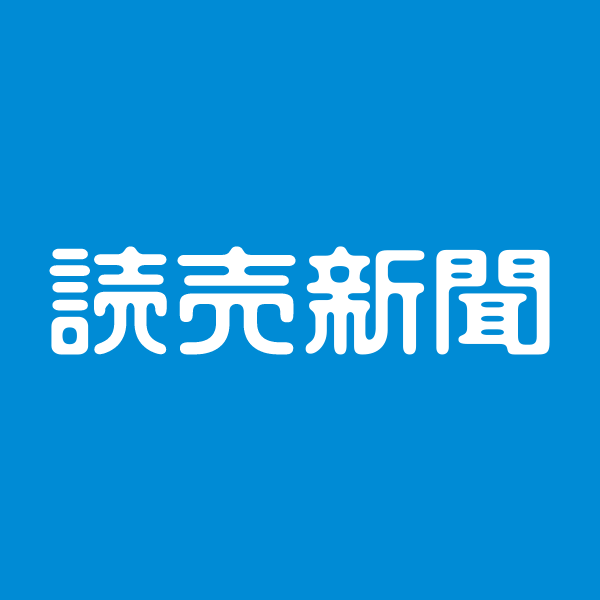ANA新ブランドは2年で幕、背景に機材不足
日本の航空最大手、ANAホールディングス(HD)は2025年10月30日、運航を始めたばかりのAirJapanブランドを26年3月で休止すると発表しました。24年2月の誕生から約2年での幕引きとなります。
ANAHDはAirJapanをANA、格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーションに続く第三のブランドと位置づけ、ボーイングの中型機787を使って成田発着のバンコク、ソウル(仁川)、シンガポールの3路線を飛ばしてきました。
しかし、2026年3月にAirJapanの全路線を運休し、ANAとピーチのデュアルブランドに回帰します。
ANAHDは背景として、ロシアのウクライナ侵攻によるロシア上空を迂回する飛行ルート採用が長期化していることや、機材納入遅延などを背景に機材不足が起きていることを挙げました。対策としてAirJapanが使っているボーイング787と人材を「ANAブランドの運航へ集約し、国際線事業規模を拡大していく判断をしました」と説明しました。
これに対し、2026年2月に設立から15年を迎えるANA全額出資子会社のピーチ・アビエーションは、日本を代表するLCCの一つとして軌道に乗っています。このため、同じANAグループでも「明暗を分けた」(航空業界関係者)との指摘が出ています。
筆者(大塚圭一郎:共同通信社経済部次長)はAirJapanブランドの休止が発表される前の2025年10月4日、前ピーチ最高経営責任者(CEO)の森 健明氏(現・ANA総合研究所副社長)からピーチを成功に導いた「内幕」を聞いていました。
森氏は筆者と同じ東京外国語大学卒で、東京都港区での同窓会「東京外語会」の会合で講演しました。ANAHDの芝田浩二社長も卒業生です。
ピーチは2025年10月時点で国内線25路線、国際線15路線を、エアバスの小型機A320シリーズで運航しています。日本初の本格的なLCCとして急成長を遂げた背景には、全日本空輸(ANA)を「完全退職」して「片道切符」で臨んだ創業メンバーの成功への固い決意と、国籍や業種を問わない多様な人材登用がありました。
「ミニANAを作ってはならない」が至上命題だった
ピーチは2011年2月、全日本空輸(ANA、現ANAホールディングス)と投資会社の合弁会社「A&F・Aviation」として設立。12年3月1日に関西―札幌(新千歳)線と関西―福岡線の運航を開始して路線を順次広げました。
筆者は当時、国土交通省記者クラブに所属して航空業界を取材しており、ANA関係者から「(ピーチ初代CEOで現・全日本空輸社長の)井上慎一さんをはじめとするA&F幹部が体育会系のノリで、『不退転の決意で新たな航空会社を作るんだ』という理由でANAを辞めて片道切符で会社の設立準備をしている」と聞いていました。
ピーチのCEOを2020年4月から3年間務めた森 健明氏は講演で、この内容を裏付ける証言をしました。井上氏から「新しい会社はANAの延長線ではダメだ。ミニANAを作ってはならない」と告げられ、ANAから「完全退職」するかどうかの選択を迫られたと振り返りました。
マニュアル作成や採用活動に当時追われていた森氏は「完全退職」の重みを認識しつつも、「迷っている時間も惜しかった」として結果的に退職を選択。「退職を機に『やってやろう』とスイッチが入った。スタートアップメンバーにとっても、『退路を断ち軌道に乗せる』という結束力が大きな力となった」と打ち明けました。
とはいえ、設立から就航までわずか1年というハードスケジュールの中で「日本にLCCの前例がなく、結構大変だった」と森氏は述懐します。そこで頼ったのが、海外の航空業界に精通した華々しい専門家たちでした。
特にフルサービスキャリアだったライアンエアーをLCCへと転換させ、その後ヨーロッパLCC最大手へ躍進させた元会長のパトリック・マーフィー氏をアドバイザーに起用したことは、「レジェンドと呼ばれている存在だけに、ピーチ成功の鍵となった」と語ります。
「経営会議は外国人アドバイザーと日本人がほぼ半々。英語で議論を戦わせた」と森氏は説明し、この外資系企業のような雰囲気が後の多様性を強みとする企業風土の礎となりました。
「多国籍」かつ「異色の経歴」多めの軍団に
航空人材が首都圏に集中している中で、大阪府泉佐野市に本社を置き、関西空港をハブ(拠点)空港として創業したピーチ。それだけに事業拡大には外国人の活用や、航空業界以外からの人材獲得が避けて通れませんでした
森氏がCEOを務めていた22年11月時点で、社員約1800人は27の国・地域出身の「多国籍軍団」となっていました。パイロットや地上スタッフで多くの外国人が活躍したほか、日本人の客室乗務員(CA)に元小学校教員や警察官出身者が就くなど多様な人材を擁していました。
「バックグラウンドが異なる集団の経営には難しさもあるが、自分の知らない経験を持つ社員と仕事をするのは楽しかった。それが当時のピーチの原動力だった」と森氏は強調しました。
ピーチは当初、ANAの出資比率が33.4%にとどまり、投資会社、官民ファンドの産業革新機構(現INCJ)がそれぞれ33.3%を出資していました。ANAHDは2017年にピーチを連結子会社化し、19年には傘下のLCCだったバニラ・エアと統合させて「ピーチ」ブランドに一本化。24年には全額出資子会社にしました。
「プランB」があったAirJapan
創業時の幹部がANAに退職届を出す「片道切符」で背水の陣を敷き、海外の航空業界のエキスパートの知見を積極的に取り込み、幅広いバックグラウンドの多国籍人材や、さまざまな業界の出身者を積極的に受け入れて成長を目指す企業風土を築いたピーチ。そんな「モーレツ」な姿勢が、本格的なLCCが不在だった日本で道なき道を切り開き、事業を大きく拡大する原動力となりました。
これに比べると、AirJapanブランドがたどった軌跡は「おっとり」していたと言えそうです。運航するエアージャパン(千葉県成田市)は既にANAHDの全額出資子会社で、ANAブランドの国際線の一部も運航しているため「後ろ盾」がしっかりしています。しかも運航しているのは、ANAグループの戦略機材であるボーイング787です。
したがって、社名をローマ字表記したAirJapanのブランドが定着しない場合には、ANAブランドへ移行するという代替案「プランB」を用意しやすい状況でした。このため、2026年3月のAirJapanの終了後は、運航に携わってきた人材も機材も比較的スムーズにANAブランドへシフトできるソフトランディング(軟着陸)が待ち受けていそうです。
他方でピーチがもしも草創期に失敗に追い込まれていた場合、日本でのLCCを定着させようと意欲を燃やしていた貴重な人材が路頭に迷うハードランディング(硬着陸)に追い込まれるリスクがありました。そんなリスクを背負い込んで成功を勝ち取った井上氏や森氏ら創業期のメンバーの「モーレツ」ぶりには感服します。
ただ、人手不足が大きな課題となっており、企業が万全な事業継続計画(BCP)を立てることが求められている今の時代には、ピーチの背水の陣はリスクが大きすぎるとも言えます。
その意味では、AirJapanブランドの寿命は約2年と短命に終わっても深手の傷を負う前に見切りを付け、ANAの機材拡充に貢献する「プランB」を選んだエアージャパンの戦略は時宜にかなっているのかもしれません。